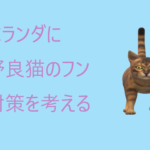2024年6月22日
毎朝8時から8時15分放送の連ドラ「虎に翼」
主人公の猪猪爪寅子役(伊藤沙莉さん)
1週間の振り返りの放送で、母 ハルさん(石田百合子さん)が亡くなるシーン。
寅子さんが子供の様に泣きじゃくる姿に自分の身内が亡くなった情景が浮かんだ。
身内が亡くなる事は、なんとも悲しいもの。
特に親が亡くなった後は、今までの心の支えを失なってしまう感覚になる。
また、母の存在は同じ女性としても父親以上に距離が近い存在だ。
ドラマの中で警察に捉えられた当時の戦争孤児は、保護されても、充分な食事や住居が与えられなかったと表現されている。
戦後の復興があって、今の豊かな時代を私たちは生きられている。
終戦後の親世代のことを昔聞いたことがある。
とにかく「食べるものがなかった」と。
来週の予告、第60話では、梅子さん:寅子さんの学友(平岩紙)が登場して、家族で派手にももめごとがありそうな予告だった。
予告の最後に亡くなった直道さんの声が!
もしや、直道さん:寅子の兄?(上川周作さん)の復活??
家庭裁判所が発足して、梅子さんの権利が守られることに期待したい。
また、もう一人の同級生のよねこさん(土居志央梨さん)との関係も改善していくのか気になるところ。
主人公の猪爪寅子(いのつめともこ)のモデルは?三淵嘉子さん」
猪爪寅子のモデルは、
三淵 嘉子さん(みぶちよしこ)1914年生まれ
戦前戦後の激動の男性中心の時代、
日本初の女性弁護士の一人で判事・家庭裁判所長や日本初女性裁判官に就任。
女性は家庭に入ることが当たり前だった時代、貞夫はとても進歩的な人物で、「ただ普通のお嫁さんにはなるな、男と同じように政治でも、経済でも理解できるようになれ。それには何か専門の仕事をもつ為をしなさい。医者になるか、それとも弁護士はどうか」
引用https://subscive.jp/mibuchiyoshiko-current/
と父親の貞夫さんの勧めもあり、法律の道に進んだ可能性がある。
ただし、たとえ親に勧められたとしても、素直に了承できるものだろうか?
ドラマのストーリーの中では、結婚に本人が乗る気ではなかったことも一因かもしれない。
しかし、昭和の後半20代であっても、”三十路”という言葉が悪い意味で、でささやかれていた。
女性は、30代になったら結婚が遅いという社会のイメージだった。
また、専業主婦という言葉も、自分の母世代から徐々に働くお母さんに変わっていった。
そして、現在は、共働きの方が多くなったと感じている。周りを見てもかなり多い。
三淵さんのように、私自身も身内に勧められて仕事を選んだ。
私の場合は、ただ単に資格があればなんとか生活できる、その一点だけ。
もしも、医者や弁護士と言われたら、それはかなりしり込みをして拒否してしまうだろう。
なぜなら、自分の時代でも男性社会だからだ。
自分の親世代よりももっと前の時代を考えるとどれほどの壁だったのだろうか。
主人公の寅子さんは、教授(穂高重親さん)との出会いと両親の革新的な考えがあって職業を選んだように感じる。
とはいえ、ドラマの中での主人公の言動と行動力には、驚かされた。
自分の親世代でも、なかなかできなかっただろう。
勇気が必要で、自分の軸を持った言動だ。
脚本家、吉田恵里香さんが、三淵嘉子さんをモデルに選んだ
脚本家・作家(小説家)1987年生まれ。
「朝ドラを書くのは長年の夢でした」とインタビューで話された吉田さん。
毎年、手帳に40個くらい「これからかなえたい夢」を書くのですが、”朝ドラの脚本を書く”ことはもう何年もかきつづけていたことでしたから。・・・
https://veryweb.jp/life/632726/
脚本家の田中さんは、朝ドラを待ち望んで実現させた方。
小説家・脚本家でテレビドラマや映画・アニメでも幅広く活躍されている。
子育てをしながらの仕事の両立には頭が下がる。
また、仕事に対する吉田さんの情熱を感じた。
吉田さんの若いころからの行動と継続力の積み重ねが夢の実現を引き寄せるのだろう。
とても、小さなお子さんがいる方とは想像もしていなかったからかもしれない。
吉田さんが描く主人公の強くたくましく生きる姿。
そして、時代の背景にある、女性のつつましく一歩下がっての様な対照的な登場人物が印象に残る。
言葉としては、「はて?」⇒「スンッ」
「スンッ」は場の空気を読むときに、私自身も使っていて今の時代でも親しみを感じた。
現代の女性は、「ハテ?」も「スンッ」もどちらも使い分けている。
ドラマを見ていても二通りに分かれるのではと感じる。
主張する人はするし、しないで協調性を大事にする人もいる。
法の下に平等という現代では、どちらも正解の行動だ。
また、ドラマでの、猪爪家と道男の関係をみると、家族の形はさまざまであった。
人情や人とのつながりの強さは、昭和の古き良き時代を感じさせる。
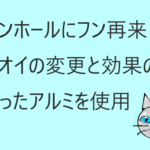
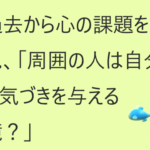

![[片付けられない20代子供]片付けの本を参考に、物を減らしてみる。クローゼットから](https://how-to-live.net/wp-content/uploads/2024/10/b531f5fc02410bf0168e4f199cb00fce-150x150.jpg)