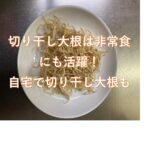こんにちは、とびおば管理人です。
3人の子供の国内修学旅行を経験しました。
高校やそれ以上になると持参する小遣いの額が自由になることが多いです。
でも、自由だからこそ悩むものです。
国内修学旅行の親御さんの参考になれば嬉しいです。
修学旅行のおこずかい、どうやって決めた?
今年、三番目の子供にいくら渡すことに決めたか、その理由と経過を書きとめます。
さらに、過去の2人子供の時はどうだったのか、思い返してみました。
結局、三人目は男子で、南九州に2泊3日で福沢諭吉様を3枚を持参させました。
これは、旅行先が地方で、(民泊や自然遊び)男子、買い物は普段から最低限です。
自由行動の時の、交通費や昼食代と出発時の朝食代、お土産代、予備的な予算を含めた額です。
子ども本人は、「不足したら心配なので一応多めに持っていきたい」と言いました。
ちなみに、余ったら、返金してもらうように話し合いました。
家族からのお土産のリクエストは、リクエストした人が予算分を渡すようにしました。
姉たちの場合は、いくらあげたか?
1番目の時は、沖縄でネット検索。
当時は、ネット情報を信じて福沢諭吉様5枚を渡しました。
結果、女子で買い物大好き、お土産は、様々な雑貨や大量のお菓子と顔のパックまで(ほとんど使わず)などで、お釣りはわずかでした。涙・涙です。
母としては、娘が楽しんでよかったと思う反面、買い物好きや旅行中の日程を良く把握していなかった。また、友だちとの金額のすり合わせができておらず。ネットの情報を過信してしまったと後悔しました。
2番目の時は、四国で、前回の経験を参考にして、田舎で買い物もそんなにできないと予測して、諭吉様3枚を渡しました。
予想通り、約1/2のお釣りを持ち帰りました。
本人曰く、「買い物するところもなくて、本当に楽しめなかった。」買いたいものを見つけるのも大変だった様子です。
子供自身は、「私はケチだから~」と笑いながら言っていましたが……親としてはあまり楽しめなかったのかと複雑です。
主に芸術作品に触れるのがテーマの修学旅行の様でした。親としては娘が残念がっていたのが、少し寂しい気分になりました。
できれば、1人目と2人目を足して2で割れると良いのですが、そこは学校とその時の修学旅行場所にもよります。
大学生を持つ周りの職場の人たちにも、当時いくら持たせたか、聞いて情報収集してみました。
諭吉様2~3枚が多く、男の子の場合は、余ってしまったようです。
また、渡して、不足した時はスマホで携帯アプリに送金という方もいましたね。これは、斬新で賢い1つの方法ですね。
性別や買い物(食べ物や雑貨、記念品など)何を好んで買い物するのか。
また、自由行動でどこに行って、何にお金を使うのか、ある程度予測するのも必要だったようです。
特に、有名なアミューズメントパークだったり海外になると食事だけでも予算が増えます。
それに加え、一緒に行動するお友達にも左右されると思います。
同じ両親の子供でも子供の個性によりこれほど違いがあり不思議な気分になります。
しかし、そこは名探偵のように予測するしかありませんね。
子供たちが楽しんで、それでいて多すぎず少なすぎずのお小遣いが理想ですね。本当に難しい。
これまでのことをまとめると、今まで、福沢諭吉様を2~3枚渡したが、国内で地方だと、3枚くらいが多い。
子供の性格や友達との話し合い、旅行先や旅行の内容で金額は変わる。
子どもと話し合って、親子が納得する金額にした方が後悔が少ない。
フォロー策として、スマホアプリ(スマホ決済)で追加という方法もあり。
親の財布の事情もありますが、子供としっかりと意見交換して、向き合って話し合いたいと思いました。
私は、家庭のお財布事情も素直に話しています。
「ここまでは、できるけど、これはちょっと厳しいかな~」など、どこまで話すかは親の考え方次第です。
お財布の紐と子供の笑顔、どちらも大切なものですね。
しかし、思い出に残る学校行事なので楽しんでほしいものです。
息子がサーフィンや旅行を堪能して笑顔で無事に帰る日を楽しみにしています。
お土産話もまた嬉しいものです。
修学旅行から戻って、実際どうだったか?
その後無事に修学旅行から戻り、お釣りを渡してくれました。
実質お小遣いの予算を2/3程を使った計算です。
その他に現地集合の駅までの交通費費は携帯のアプリ決済にチャージしました。
現地で食事をしたり、食べ物をお土産に持ち帰りました。
何が旅行で一番楽しかったか聞くと、サーフィンだった様です。初めてでしたが、教え方が上手で何とか波に乗れた感じです。
思ったよりも、お土産話を聞けて楽しかったです。お水が美味しかったとの感想が印象的でした。確かに鹿児島はミネラルウォーターを販売していますね。
最後まで見ていただきありがとうございます。
お子さんが楽しい思い出作りができて笑顔で戻ってくる日がたのしみですね。
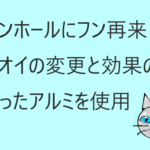
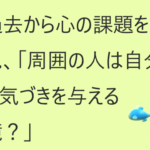
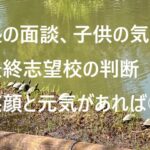
![[片付けられない20代子供]片付けの本を参考に、物を減らしてみる。クローゼットから](https://how-to-live.net/wp-content/uploads/2024/10/b531f5fc02410bf0168e4f199cb00fce-150x150.jpg)